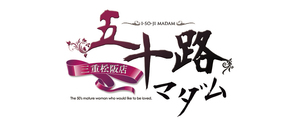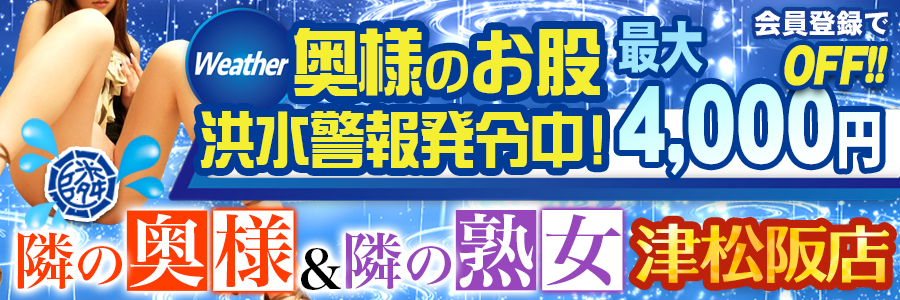写メ日記
(詳細)恋と自然選択説と…
3/18(火) 22:48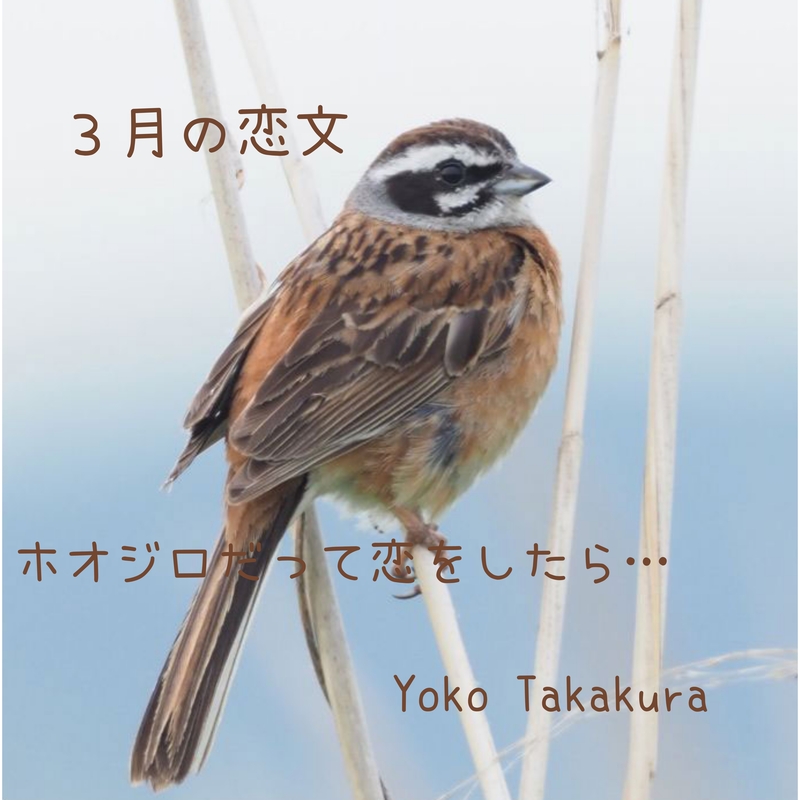
こんばんは。お疲れ様です。
1月の恋文で"野鳥"を綴りましたので、
今回も"野鳥"で綴ります。
「高槻の こずゑにありて 頬白の
さへづ(エズ)る春と なりにけるかも」
これは歌人、島木赤彦氏の作品です。
意味は、
ホオジロがケヤキの木(高木樹)に止まって
鳴いているよ。やっと春が来そうだなぁ…
といったところでしょうか…
(随分簡単にしてしまいました…)。
というわけで、この作品は全く"恋の歌"
ではありません。でも、この作品を敢えて
"恋の歌"として取り上げました。
この作品は、発表された時に、
ある疑問が投げかけられました。
それは「ホオジロは地上や背の低い木で
生活しているので、高いこずえには行かないよね…(作者が想像で作った)」
という指摘です。
でも、野鳥研究家さんからは
「ホオジロのオスは、メスへの求愛や、
縄張りの主張のために、春先のみ見通しの良い場所でさえずる事がありえる」
という見解も示されています。
メスのために高いところに行く…
なんとも健気ではないか…
・
・
そうなのか?
私はこの野鳥研究家さんの見解から、
1つの説を思い出しました。
それはダーウィン大先生の"自然選択説"です。
そう、キリンの首の説です。
この作品は大正13年(1924年)に
発表されました。ということは、
100年くらい経っているんですね。
最近の説によると
「ホオジロの巣は季節を追って巣の高さを
変える(季節を追うごとに巣の位置が
高くなっていく)」
※理由としては、ヘビやイタチなどの敵から
巣のひなを守るためとか、成長する雑草から
巣を守るためとからしいです。
「一夫二妻の可能性がある」
とか、あるみたいですね。
これらの説が、もともとの性質なのか、
100年の間に変わってきた性質なのかは
分かりません。でももし、100年の間に、
変わってきた性質ならば、ホオジロは
高い所で生活するようになるかもしれませんね
しばらくは「高い所で生活するメリット」と
「低い所で生活するメリット」の"鞘当て"が
起きるかもしれませんね…?
ダーウィン先生、どう思われますか?
なんてね(笑)
恋文のコーナーなのに相変わらず
「長い」「つまらん」「色気がない」
で、すいません…(泣)。
そういえば、キリンの首の説にも
"新説"が発表されましたね。
ってそろそろやめときますね(笑)。
最後まで読んでくださり
ありがとうございました。
やっぱり生き物は不思議で面白いですね
それではまた…おバイチャ♪
高倉 洋子













 お気に入り登録
お気に入り登録